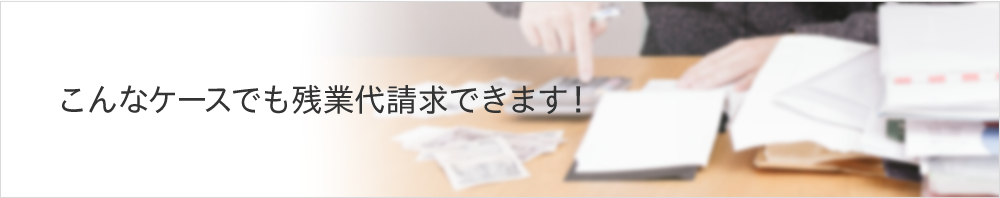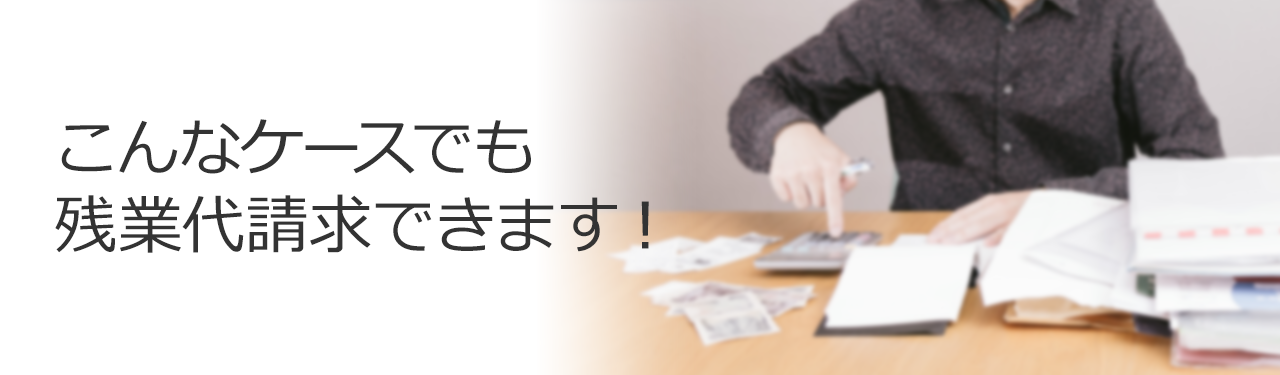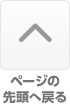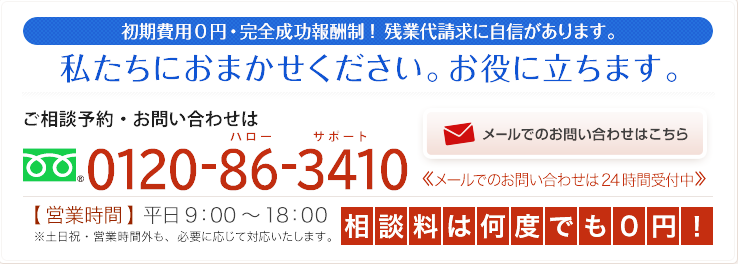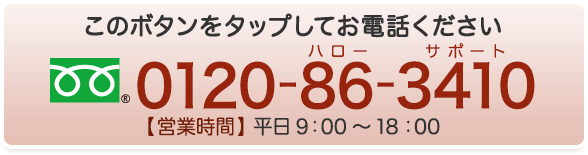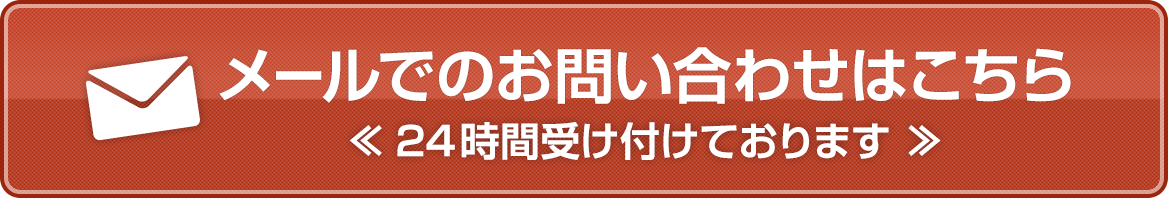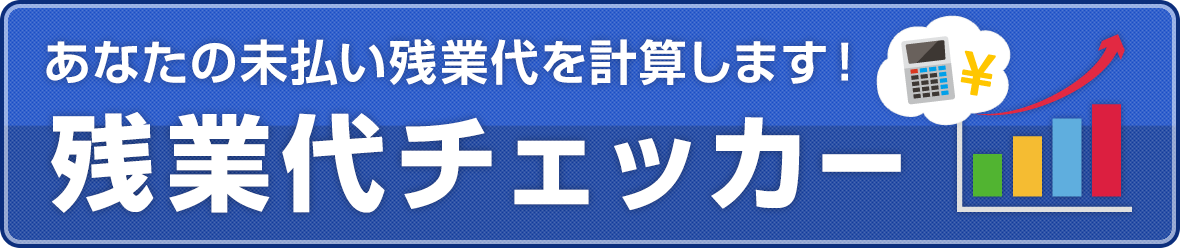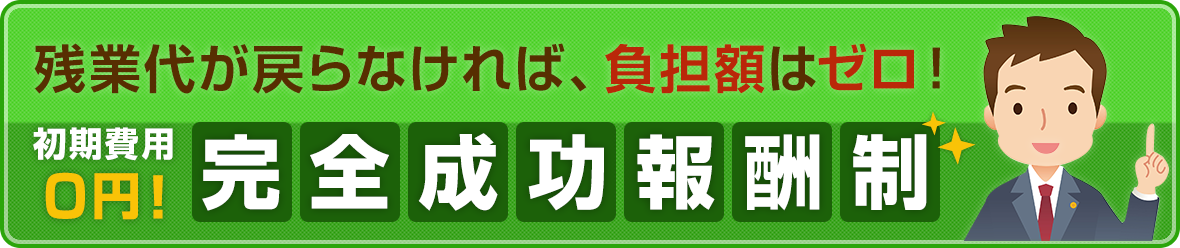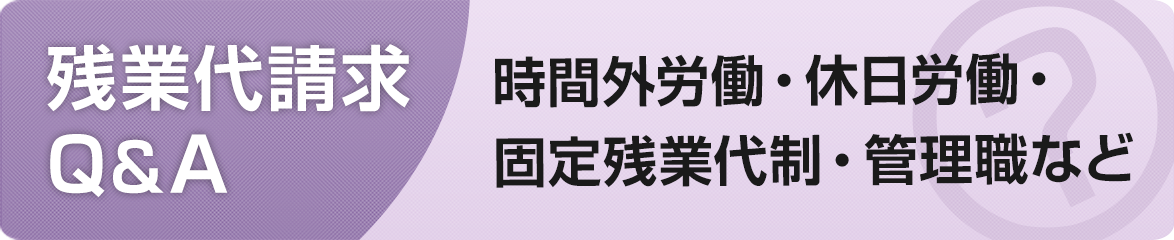こんなケースでも残業代請求できます!
「管理職」でもあきらめない!
 「部長」「課長」「係長」「店長」「工場長」などの役職名や肩書きがついている、一般的に管理職と呼ばれている人に対して、会社側(相手方)が「管理職だから、残業代は出ない」と説明している場合があります(名ばかり管理職)。
「部長」「課長」「係長」「店長」「工場長」などの役職名や肩書きがついている、一般的に管理職と呼ばれている人に対して、会社側(相手方)が「管理職だから、残業代は出ない」と説明している場合があります(名ばかり管理職)。
しかし、あきらめる必要はありません。法律上「労働条件の決定その他労働管理について、経営者と同じ立場にある者」とされている管理監督者にあたらない限り、残業代を請求できます。
管理監督者にあたるかどうかは、単に役職名や肩書きなどの名目だけではなく、実際の仕事内容や権限の大きさ、出社・退社時間が自由かどうか、給与条件・待遇など、その実態によって決まります。
また、「役職手当」が支払われているからといって、残業代を支払わなくてもよいとは限りません。
なお、もし仮に管理監督者にあたる場合でも、深夜労働については残業代を請求できます。
「年棒制」でもあきらめない!
会社側(相手方)が年俸制を導入していたとしても、法定労働時間(1日8時間 または
1週間40時間)を超えて働いたような場合には、原則として割増賃金を請求できます。
割増賃金は、年俸額を12か月で割って月額を求め、さらに時給換算し割増率をかけて算出します。
「裁量労働制」「みなし労働制」「フレックスタイム制」でもあきらめない!
「裁量労働制を採用している」「みなし労働制だから」「フレックスタイム制(フレックス制)を導入している」などを理由に、残業代が支払われていないということがあります。
もし、会社側(相手方)が裁量労働制やみなし労働制などを導入していたとしても、
- 裁量労働制やみなし労働制などを導入できない仕事内容である
- その制度を導入するための労使協定を結んでいないなど、法律で定められた手続きがとられていない
- 実際の勤務状態が、裁量労働制やみなし労働制などにふさわしくない
といったような場合には、会社側(相手方)の定めた制度そのものが無効だとして、残業代を請求できます。
会社側(相手方)の定めた制度が有効だとしても、みなし労働制は「1日○時間働いたものとみなす」というように、あらかじめ労使協定などによって定められるものですので、みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間 または 1週間40時間)を超えている場合には、原則として割増賃金を請求できます。
その他のケースでもあきらめない!
会社側(相手方)が固定残業代制を採用していたり、「残業代は▲▲手当に含まれている」「うちの残業代は〇〇円とみなしている」と言ったりしていても、すぐにあきらめる必要はありません。
実際に、会社の設定した固定残業代制や手当制そのものが無効なケースも多くあります。
会社の定めた制度に法的な不備がある場合
会社によって固定残業代制の形態はさまざまですが、会社の定めた制度が下記①、②の両方を満たしていない場合には、固定残業代制そのものが無効となり、割増賃金を請求できる可能性があります。

給与明細や就業規則、労働契約などで、残業代にあたる部分が明確に区分されている。
(○時間分の割増賃金を定額で支払う、▲▲手当には○時間分の残業代が含まれる、などの明確な規定が必要)

会社で定められた固定残業代よりも、実際に働いた時間分の残業代の方が多くなる場合には、その超過した差額を支払うことについて合意されている。
会社の定めた制度が有効で、会社から毎月一定額の固定残業代が支給されている場合
その支給額よりも実際に働いた時間分の残業代の方が多くなる場合には、超過した差額を請求できます。